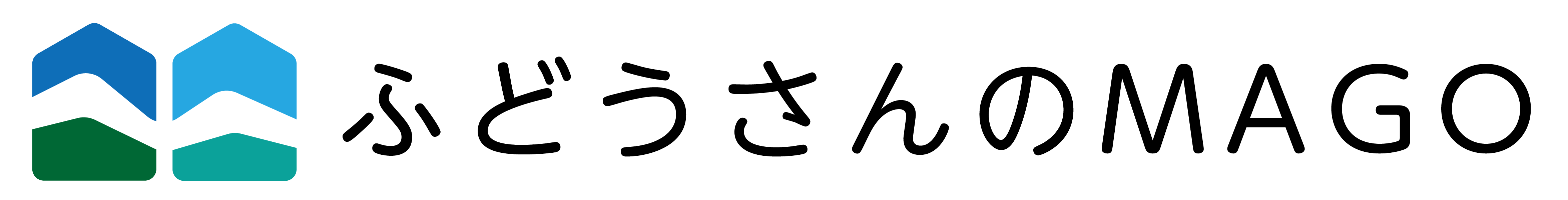不動産を相続した場合、状況に応じてさまざまな選択があるでしょう。不動産の相続にはトラブルが起きがちであり、また相続税の負担など難しい問題が生じます。そこで相続税対策や売却するメリットなど、相続不動産に関する基礎知識をご紹介します。相続不動産でお悩みの方は是非、名古屋市のふどうさんのMAGOまでご相談ください。
相続不動産でこのようなお悩みありませんか?
●相続した空き家が遠方にあり管理できていない
●早く売却して現金化したい
●親から継いだ大切な土地なので少しでも高く売却したい
●実家の遺品・家財道具の処分・整理ができない
●不動産を相続したが使い道もなく維持費がかかっている
●売却時の税金や確定申告をどうすればいいかわからない
●遺産として不動産があるので現金化して公平に分割したい
●不動産を兄弟姉妹で受け継いだが話が平行線で困っている
●親族で相続した不動産を子どもの代に残すのが不安
●生きている間にできる相続税対策はないだろうか
相続不動産でのお悩みランキング
1位 遺品整理・家財処分
2位 相続登記
3位 遺産分割・相続財産の算出
他にもこんなお悩み・ご相談があります。相続人が不明、負の資産がある、借地権・底地共有持分の一部売却など、少子高齢化が進む日本において相続はとても身近な問題です。たとえば、現金であれば公平に分割できますが、不動産は分割しにくく親族同士でトラブルになることも珍しくありません。不動産を相続は法律的にも複雑になりやすく「何から始めたらいいかわからない」という方も多いことでしょう。
何より大事な不動産相続の事前準備
相続でもめるのが多いケースは、相続財産が5,000万円以下とされています。2023年に相続トラブルを起こした約8割のケースが、遺産額5,000万円以下というデータがあります。(参考:司法統計年報|最高裁判所事務総局)つまりごく一般的な家庭でも、争いが生じていることがわかります。相続財産が多いから争いが生じるわけではない点を押さえましょう。

相続 というと、相続した後の事を考えがちですが、実際は生前での相続準備の方がはるかに重要です。相続の話自体が「触れたくない」話題という事もあり、なかなか親族の間でも切り出すのは勇気のいる事だと思います。人によっては縁起でもない事として避けてしまう事も。ですが将来の事を考え、まだ非相続人の判断能力がしっかりしているうちに資産整理をし、正式に遺言を残しておきましょう。
相続の中でも特に厄介な不動産
遺言書や遺産分割協議で取り決めがない場合、不動産も法定相続分に基づいて相続されます。しかし家を分割して使用することは物理的に不可能です。不動産の扱いは難しく多くの人がその処理に困ることになります。更に問題を複雑にする要素があります。
不動産の評価の難しさ
不動産の評価は時価の評価となります。土地は同じものは一つとして世の中に存在しない特定物で、土地ごとに異なります。交通利便性や周辺環境なども鑑みつつ時価を算出するのは非常に難しいことです。また、家の評価の決め方が問題になることがあります。例えば「代償分割」で遺産分割協議した場合、これが4,000万円だと、長女は次女に代償金として2,000万円支払えば良いことに。一方で家の土地建物の価額が5,000万円に変われば、長女は代償金として2,500万円支払わなければなりません。つまり、代償金を決めるもとになる不動産の価額を安く見積もれば長女に有利となり、反対に高く見積もると次女に有利になります。相続不動産の評価の仕方はとても難しく、親族でもめる原因の一つになります。
CHECK UP 1
不動産の評価で揉める
不動産の評価額は、遺産分割協議成立時点の時価が原則です。また相続税評価額(路線価)は、実際の取引価格(実勢価格)の8割程度、役所の固定資産税評価額は、時価の7割程度を目途に設定されていますので、時価よりも低くなります。依頼する士業によりますが、この曖昧な評価額の算出方法が、相続における不信感が生まれる原因の一つになります。

分割のしにくさ
現金資産と違い、分割しにくいのも大きな特徴です。受け継ぐ人が一人なら問題ありませんが、兄弟姉妹で不動産を相続すると単純に分けて「共有持ち分」にする場合が多いです。しかし「共有名義の不動産」を売却するには名義人全員の合意が必要なのです。一人は売却を主張、もう一人は賃貸にすると主張、もう一人は空き家のまま残したいと主張。こうなると話は平行線です。
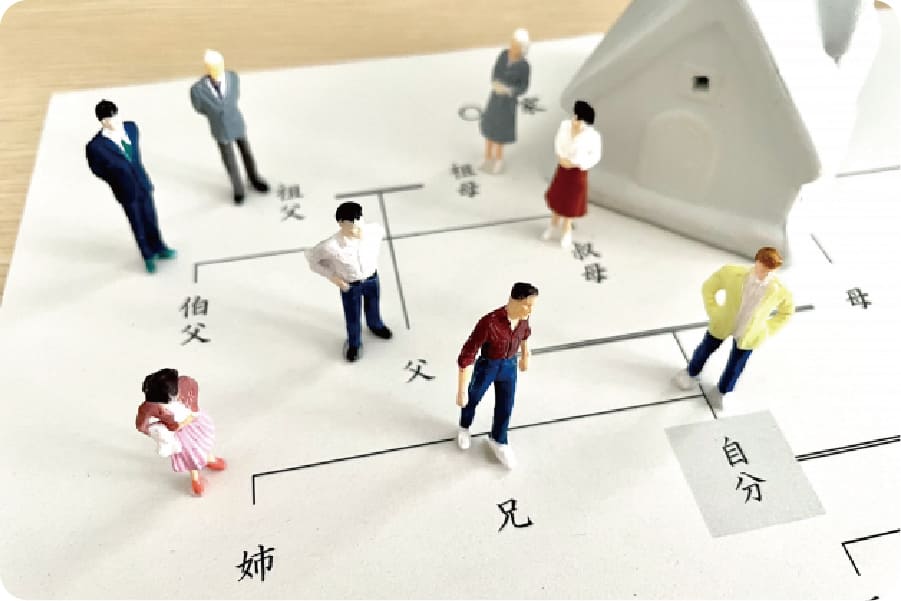
具体的な不動産相続対策
①遺産分割対策 ②節税対策 ③納税対策 ④認知症対策
①遺産分割対策
財産を誰にどう分けるか、特に不動産の場合は事前対策が必要です。現金化するのか?誰が所有するのか?売らずに現金で配分するか?など、誰が・何を・どう相続するかを全員で決めることが大切です。相続不動産で揉める原因の大多数は「評価で」「分割方法」です。分割の仕方は具体的には「代償分割」「換価分割」「現物分割」「共有分割」があります。説明は割愛しますが特に注意すべきは「共有分割」です。複数兄妹で不動産を受け継いだ場合など、兄妹全員の同意がないと売却できない上、所有する場合でもその維持費を誰がどう払うのか?誰が運用するのか?共有者全員の意見を折衝しないといけません。また、それがさらに次の世代に渡った場合は、状況はより複雑化します。例えば受け継いだ兄妹全員に3人ずつ子供がいた場合、次に相続が起きたとき9人の共有持ち分になってしまう訳です。こうなると状況の整理と解決は困難を極めます。また、共有状態の不動産は「訳あり物件」として市場から敬遠される傾向が強いので、手放すことも叶わないリスクが伴います。
②節税対策
また相続には相続税が発生します。生前にできる対策により、そうした相続税額を減らす事できます。
●暦年贈与
説明は割愛いたします。
●相続時精算課税
説明は割愛いたします。
③納税対策
相続税が発生する場合、相続から10ヶ月以内に「現金一括」納付が原則です。特に相続財産の大半が不動産という場合には注意が必要です。財産は受け継いだのに相続税用の現金が無いという状況に陥りやすくなってしまいます。そうなる前に「所持不動産の現状把握」はもちろん、「負の資産」も掌握して、財産整理しておきましょう。
④認知症対策
被相続人の認知症が発症すると、遺言書や生前贈与、不動産の売却を行った場合「正常な判断がされていなかった」とみなされ、無効になる可能性があります。認知症であることで相続手続きに問題が起こるケースが増えています。認知症の発症リスクに備え、被相続人の意思能力がはっきりとしているうちに検討しましょう。
予め考えておきたい家族信託
もし親が認知症を発症したら、不動産は売却できる?親が認知症になってしまうと判断能力が低下しているため、所有者である親は売買契約を結ぶことができません。 家族であっても、不動産は勝手に売却することはできません。家族信託とは、親が認知症などによって家族が財産を管理できなくなった場合に備えて、事前に財産の管理・売却の権限を家族に与える制度です。

財産を「利益を受ける権利」と「管理運用する権利」に分けて、後者を家族に管理・運用してもらう仕組みです。認知症になった場合、管理や処分の方向性について、親自身の意思を最大限反映させることができます。
認知症による財産凍結を避けたいケース
認知症により判断能力が低下すると、本人名義の預貯金の引き出しや不動産の売却などができなくなる「資産凍結」の問題が生じます。家族信託を活用することで、このような事態を防ぐことが可能です。成年後見制度の場合、身内であっても管理人を自由に選べません。また資産を自由に動かしにくいという制約があります。家族信託であれば契約内容に沿って自由に資産を動かせますので、成年後見制度よりも柔軟性が高いといえます。
資産の凍結を防ぎ、柔軟な運用が可能に
家族信託を使うことで資産の凍結を防ぎ、柔軟な運用が可能になるとともに、遺言では一次相続人の指定しかできないが、家族信託では二次相続以降の承継先も指定することができることもメリットです。また、家族信託では信託契約に基づいて財産管理が受託者に一元化され、相続人全員による遺産分割協議が不要になり、相続発生時の手続もスムーズに進めることができます。
相続不動産の流れ
不動産を相続したものの「どうしたらいいかわからない」という方も多いのではないでしょうか。ここでは不動産相続の流れをわかりやすくご紹介します。







遺言書が残されておらず相続人が2人以上いる場合、遺産の分け方を話し合って決める必要があるため遺産分割協議を行います。遺産分割協議にはすべての相続人が参加する必要があります。
遺産分割協議の形式に特に決まりはなく、相続人が直接集まって協議する場合もあれば、メールや電話で話をまとめても構いません。また、遺産分割協議に期限はないため、仮にいつまでも話し合いがまとまらず合意できなくても罰則などはありません。ただし、相続税の申告期限である10ヶ月までに遺産分割協議が終わっていない場合、いったん法定相続分に応じた相続税申告の手続きをとらないと不利益を被ることがある点には注意が必要です。





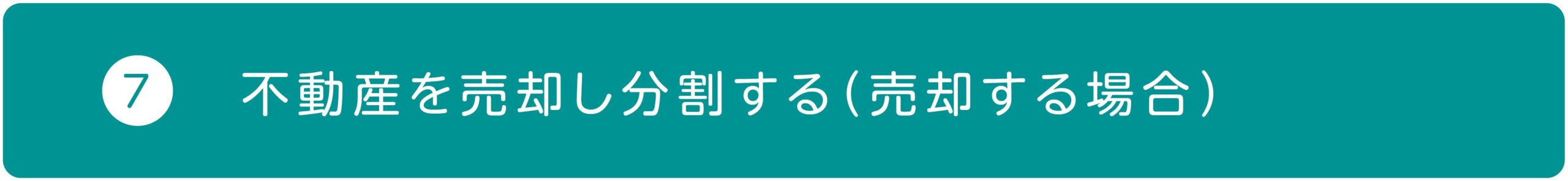


CHECK UP 2
不動産を代償分割する場合、贈与税はかかる?
遺産分割協議書に「代償分割により代償金を支払う」ときちんと記載しておきましょう。代償財産の種類や金額、支払い期限などを遺産分割協議書に記載することで贈与ではないことが明確になり、贈与税の課税対象にならなくなります。

不動産の相続や売却に必要な書類
不動産の相続に必要となる書類は以下の通りになります。
相続登記の申請書類
相続人全員の住民票抄本
相続人全員の印鑑証明書
被相続人の住民票の除票
不動産の全部事項証明書
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の住民票謄本
被相続人の戸籍謄本(出生から死去まで)
不動産の固定資産評価証明書
空き家を相続する場合の選択肢
空き家を相続した際、活用方法や手放し方を含めて以下の選択肢が考えられます。それぞれのメリットとデメリットを理解したうえで、最適な判断を行うことが大切です。
| 売却する | 空き家を売却することで固定資産税や管理費用などの継続的な負担を解消できます。特に、需要の高いエリアであれば高値で売却できる可能性があります。一方、売却益が発生した場合には譲渡所得税が課されることがあるため事前に税務の確認が必要です。 |
| 賃貸する | 空き家を賃貸物件として家賃収入を得る方法もあります。賃貸物件として貸し出す場合には修繕やリフォームを行い、居住可能な状態にする必要があります。また、入居者管理や賃貸契約に伴う手間も発生するため、不動産管理会社の利用を検討すると良いでしょう。 |
| 居住する | 空き家に自身や家族が居住する選択もあります。思い入れのある実家などの場合は、この選択肢は心理的な満足感を得られるケースも多いです。ただし、老朽化した住宅の場合リフォーム費用が高額になる可能性もあり、費用対効果を見極める必要があります。 |
| 寄与する | 自治体やNPO法人に寄付することで、空き家を有効活用してもらう選択肢もあります。寄付には社会貢献の側面がありますが、寄付先が受け入れる条件を満たす必要があり、手続きも容易ではないことを留意しておきましょう。 |
| 相続放棄 | 空き家を含む財産を相続放棄することで、負担を回避する方法です。相続放棄を選択する場合、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。ただし、他の財産も放棄することになるため、慎重な判断が求められます。 |
不動産相続や売却でかかる費用と税金
相続時にかかる6つの税金
①相続税
相続税は、被相続人が遺した財産を受け継ぐ際に課される税金です。財産には不動産、現金、有価証券などが含まれ、空き家もその一部に該当します。相続税は、基礎控除額を超えた分に対して累進課税が適用されます。
たとえば、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と計算され、これを超える財産部分に税率が適用されます。空き家の規模や立地などによっては不動産の価値が高いとみなされ、相続税負担が高額となることもあるため、事前に不動産評価を確認することが重要です。
②登録免許税
登録免許税は、相続により不動産の所有権を移転登記する際に課される税金です。いわゆる「相続登記」です。原則として固定資産評価額の0.4%が税率として適用されます。
③固定資産税・都市計画税
空き家を所有する限り、毎年固定資産税と都市計画税を支払う必要があります。固定資産税は土地や建物の評価額に基づいて算出され、市町村が課税します。一方、都市計画税は主に市街化区域内の不動産に対して課され、固定資産税の評価額に一定の税率を乗じた額となります。
④譲渡所得税
譲渡所得税の税率は、所有期間によって異なります。所有期間が5年以下の場合には「短期譲渡所得」となり、税率は30%です。5年を超える場合には「長期譲渡所得」となり、税率は15%と低くなります。
例えば、売却価格が1億円、取得費が5,000万円、譲渡費用が100万円の場合、
1億円−5,000万円−100万円=4,900万円になり、
4,900万円に対して所得税が課税されます。
不動産譲渡所得にかかる所得税と住民税(地方税)は、事業所得や給与所得とは別々に計算されるため、「分離課税」と言われています。不動産を譲渡して利益が出た時は、その利益に対して所得税と住民税が譲渡所得として課税されます。
⑤住民税(相続した不動産を売却した後に発生する税金)
住民税の税率は、所有期間によって、譲渡所得税の税率と同様に異なります。所有期間が5年以下であれば「短期譲渡所得」となり、税率は9%です。5年超であれば「長期譲渡所得」となり、税率は5%と低くなります。
⑥復興特別所得税(2037年まで所得税に加算される税金)
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するための税金です。2037年までの間、所得税額に2.1%が上乗せされます。
相続して売却する場合に利用できる特例と、支払う税金を減らすためのコツ
空き家を相続する際、以下の特例や制度を活用することで税負担を軽減できる可能性があります。特に譲渡所得税には税額を減らせる特例が用意されているため、実際に支払う税額は、計算した金額よりも少なくなるケースが多いです。

売却時は譲渡所得3,000万円特別控除を活用する
この特例では、譲渡所得(売却益)から最大3,000万円を控除できるため、売却後の税負担を大幅に軽減できます。適用条件を満たせば、多くのケースで相続人にとって大きなメリットがあります。ただし、適用を受けるためには一定の条件が必要になりますので、事前に条件を満たすか確認しておきましょう。
適用を受けるための主な条件は次のとおりです。
●相続や遺贈によって財産を得た者(相続人)であること
●財産を相続するにあたり、相続税が課されたこと
●相続開始日から3年10か月以内に売却すること
配偶者控除
被相続人の配偶者は優遇されていて、遺産総額が1億6,000万円までは相続税が控除されます。さらにこれを超えたとしても、法定相続割合相当分まで相続税は控除されるため、ほぼ税金がかかることはありません。
小規模宅地の特例の適用
小規模宅地等の特例は、相続税の負担を大幅に軽減する制度で、被相続人が居住や事業に使用していた宅地を相続する際に適用されます。この特例を利用することで一定の面積までの宅地に対する相続税評価額を最大80%減額可能です。具体的には、居住用宅地であれば最大330㎡まで、事業用宅地であれば最大400㎡までが対象です。結果、相続税が大幅に抑えられ、高額な土地相続の場合には重要な制度となります。
この特例を適用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
| 被相続人がその宅地を居住用 または事業用に使用していたこと | 被相続人が亡くなる直前まで、その宅地を自らの居住用または事業用として使用していたことが求められます。 ただし、被相続人が老人ホームなどに入所していた場合でも、一定の要件を満たせば適用対象となることがありますので、詳しくは専門家に確認することをお勧めします。 |
| 相続人がその宅地を 継続して利用すること | 相続人が相続後も引き続きその宅地を居住用または事業用として使用することが必要です。たとえば、被相続人の自宅を相続した場合、相続人自身がその家に住み続けることが求められます。 事業用の場合も同様に、相続人がその場所で事業を継続することが条件となります。この継続利用の要件を満たさない場合、特例の適用は受けられません。 |
| 相続税の申告期限まで その宅地を保有していること | 相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)まで、相続人がその宅地を所有し続けることが求められます。この期間内に宅地を売却すると、特例の適用が受けられなくなる可能性があります。 したがって、特例の適用を受けるためには、少なくとも申告期限までは宅地の所有と使用を継続することが重要です。 |
| 被相続人と生前に同居していること | 原則として、被相続人と生前に同居していた親族が相続する場合に、小規模宅地の特例を受けることができます。一方で、「家なき子特例」を利用する場合は、必ずしも同居が必要ではありません。 |
家なき子特例について
「家なき子特例」とは、一定の条件を満たすことで同居していなくても特例が受けられる制度です。この特例は、自宅を所有していない相続人に対して適用されます。この特例を利用することで、大きな税負担を避けることが可能です。ただし、特例適用には事前の計画と必要書類の準備が重要です。加えて、この特例の適用状況はケースバイケースで異なるため、士業の方のアドバイスを受けることをお勧めします。
家なき子特例は、以下の要件を満たす場合に適用されます。
●相続人自身や配偶者が相続開始前3年以内に、自らの所有する住宅に住んでいなかったこと。
(賃貸住宅に住んでいる場合など)
●被相続人の居住用宅地を相続し、自らの居住用として使用すること。
●過去に同一生計内の親族から住宅を贈与されたことがないこと。
参照 朝日新聞デジタル:https://www.asahi.com/ads/sozoku_vs/column/tax/25/
参照 国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
【おさらい】不動産は相続後3年以内の売却がおすすめ
相続税を費用にする特例は、譲渡所得の計算時に3,000万円を控除でき、課税対象額を抑えられる制度です。不動産を相続後3年以内に売却すると「相続税の取得費加算の特例」が適用され、相続不動産の売却により生じた譲渡所得から、相続税の一部を「売却にかかった費用」として差し引けます。
特例が適用されると、課税対象となる金額がさらに少なくなることに。結果的に、譲渡所得税の節税につながります。
譲渡所得 = 売却金額 −(取得費 + 譲渡費用)− 3,000万円(特別控除)
⇒ 譲渡所得が3,000万円以下なら譲渡所得税は課税されない
つまり、特例を活用し被相続人の空き家を売却すれば、譲渡所得が3,000万円以下なら譲渡所得税は課税されないということです。3年以内に土地を売却するためにはスムーズな遺産分割と早めの行動が必要です。相続した不動産を売却して、譲渡益が発生した場合には、確定申告を行う必要があります。不動産を売却する際には、取得費の確認や特別控除の適用要件の確認など、確認すべき事項が多く、確定申告書に添付する書類も多いため、手続きが煩雑になりがちです。
そのため、不動産を売却した場合には、確定申告が必要かどうか、また、特別減税の適用を受けられるかどうかなど、必要な手続きを正しく行うためにも、早めに士業の方に相談することをおすすめします。
※他の相続人が相続税を払っており、土地を引き継いだ人に相続税が発生していなければ特例は利用できません
※空き家の3,000万円の特別控除との併用はできません。


不動産を相続した場合、状況に応じてさまざまな選択があるでしょう。不動産の相続にはトラブルが起きがちであり、また相続税の負担など難しい問題が生じます。そこで相続税対策や売却するメリットなど、相続不動産に関する基礎知識をご紹介します。相続不動産でお悩みの方は是非、名古屋市のふどうさんのMAGOまでご相談ください。
相続不動産で
このようなお悩みありませんか?
●相続した空き家が遠方にあり
管理できていない
●早く売却して現金化したい
●親から継いだ大切な土地なので
少しでも高く売却したい
●実家の遺品・家財道具の処分・整理ができない
●不動産を相続したが使い道もなく
維持費がかかっている
●売却時の税金や確定申告を
どうすればいいかわからない
●遺産として不動産があるので
現金化して公平に分割したい
●不動産を兄弟姉妹で受け継いだが
話が平行線で困っている
●親族で相続した不動産を
子どもの代に残すのが不安
●生きている間にできる
相続税対策はないだろうか
相続不動産でのお悩みランキング
1位 遺品整理・家財処分
2位 相続登記
3位 遺産分割・相続財産の算出
他にもこんなお悩み・ご相談があります。相続人が不明、負の資産がある、借地権・底地共有持分の一部売却など、少子高齢化が進む日本において相続はとても身近な問題です。たとえば、現金であれば公平に分割できますが、不動産は分割しにくく親族同士でトラブルになることも珍しくありません。不動産を相続は法律的にも複雑になりやすく「何から始めたらいいかわからない」という方も多いことでしょう。
何より大事な不動産相続の事前準備
相続でもめるのが多いケースは、相続財産が5,000万円以下とされています。2023年に相続トラブルを起こした約8割のケースが、遺産額5,000万円以下というデータがあります。(参考:司法統計年報|最高裁判所事務総局)つまりごく一般的な家庭でも、争いが生じていることがわかります。相続財産が多いから争いが生じるわけではない点を押さえましょう。

相続 というと、相続した後の事を考えがちですが、実際は生前での相続準備の方がはるかに重要です。相続の話自体が「触れたくない」話題という事もあり、なかなか親族の間でも切り出すのは勇気のいる事だと思います。人によっては縁起でもない事として避けてしまう事も。ですが将来の事を考え、まだ非相続人の判断能力がしっかりしているうちに資産整理をし、正式に遺言を残しておきましょう。
相続の中でも特に厄介な不動産
遺言書や遺産分割協議で取り決めがない場合、不動産も法定相続分に基づいて相続されます。しかし家を分割して使用することは物理的に不可能です。不動産の扱いは難しく多くの人がその処理に困ることになります。更に問題を複雑にする要素があります。
不動産の評価の難しさ
不動産の評価は時価の評価となります。土地は同じものは一つとして世の中に存在しない特定物で、土地ごとに異なります。交通利便性や周辺環境なども鑑みつつ時価を算出するのは非常に難しいことです。また、家の評価の決め方が問題になることがあります。例えば「代償分割」で遺産分割協議した場合、これが4,000万円だと、長女は次女に代償金として2,000万円支払えば良いことに。一方で家の土地建物の価額が5,000万円に変われば、長女は代償金として2,500万円支払わなければなりません。つまり、代償金を決めるもとになる不動産の価額を安く見積もれば長女に有利となり、反対に高く見積もると次女に有利になります。相続不動産の評価の仕方はとても難しく、親族でもめる原因の一つになります。
CHECK UP 1
不動産の評価で揉める
不動産の評価額は、遺産分割協議成立時点の時価が原則です。また相続税評価額(路線価)は、実際の取引価格(実勢価格)の8割程度、役所の固定資産税評価額は、時価の7割程度を目途に設定されていますので、時価よりも低くなります。依頼する士業によりますが、この曖昧な評価額の算出方法が、相続における不信感が生まれる原因の一つになります。

分割のしにくさ
現金資産と違い、分割しにくいのも大きな特徴です。受け継ぐ人が一人なら問題ありませんが、兄弟姉妹で不動産を相続すると単純に分けて「共有持ち分」にする場合が多いです。しかし「共有名義の不動産」を売却するには名義人全員の合意が必要なのです。一人は売却を主張、もう一人は賃貸にすると主張、もう一人は空き家のまま残したいと主張。こうなると話は平行線です。
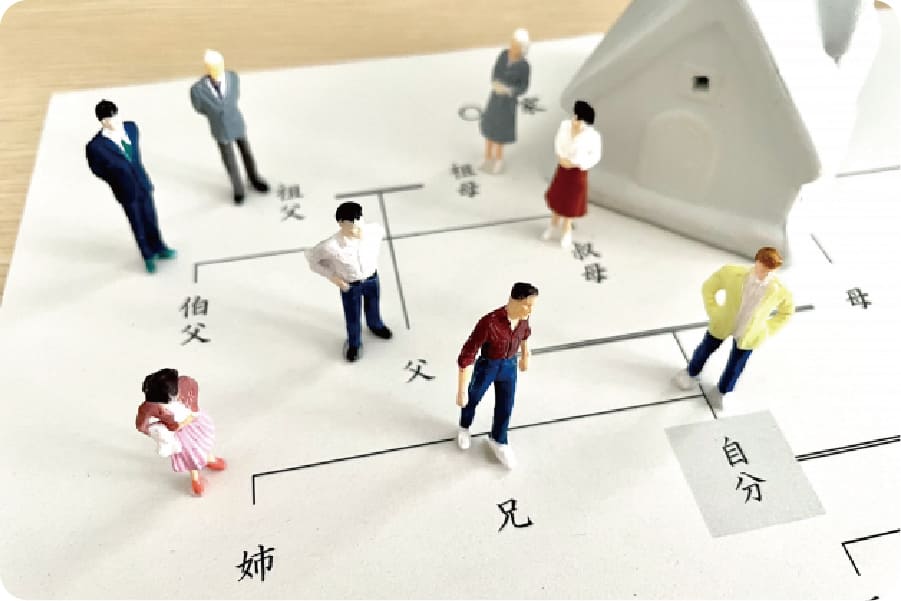
具体的な不動産相続対策
①遺産分割対策 ②節税対策
③納税対策 ④認知症対策
①遺産分割対策
財産を誰にどう分けるか、特に不動産の場合は事前対策が必要です。現金化するのか?誰が所有するのか?売らずに現金で配分するか?など、誰が・何を・どう相続するかを全員で決めることが大切です。相続不動産で揉める原因の大多数は「評価で」「分割方法」です。分割の仕方は具体的には「代償分割」「換価分割」「現物分割」「共有分割」があります。説明は割愛しますが特に注意すべきは「共有分割」です。複数兄妹で不動産を受け継いだ場合など、兄妹全員の同意がないと売却できない上、所有する場合でもその維持費を誰がどう払うのか?誰が運用するのか?共有者全員の意見を折衝しないといけません。また、それがさらに次の世代に渡った場合は、状況はより複雑化します。例えば受け継いだ兄妹全員に3人ずつ子供がいた場合、次に相続が起きたとき9人の共有持ち分になってしまう訳です。こうなると状況の整理と解決は困難を極めます。また、共有状態の不動産は「訳あり物件」として市場から敬遠される傾向が強いので、手放すことも叶わないリスクが伴います。
②節税対策
また相続には相続税が発生します。生前にできる対策により、そうした相続税額を減らす事できます。
●暦年贈与
説明は割愛いたします。
●相続時精算課税
説明は割愛いたします。
③納税対策
相続税が発生する場合、相続から10ヶ月以内に「現金一括」納付が原則です。特に相続財産の大半が不動産という場合には注意が必要です。財産は受け継いだのに相続税用の現金が無いという状況に陥りやすくなってしまいます。そうなる前に「所持不動産の現状把握」はもちろん、「負の資産」も掌握して、財産整理しておきましょう。
④認知症対策
被相続人の認知症が発症すると、遺言書や生前贈与、不動産の売却を行った場合「正常な判断がされていなかった」とみなされ、無効になる可能性があります。認知症であることで相続手続きに問題が起こるケースが増えています。認知症の発症リスクに備え、被相続人の意思能力がはっきりとしているうちに検討しましょう。
予め考えておきたい家族信託
もし親が認知症を発症したら、不動産は売却できる?親が認知症になってしまうと判断能力が低下しているため、所有者である親は売買契約を結ぶことができません。 家族であっても、不動産は勝手に売却することはできません。家族信託とは、親が認知症などによって家族が財産を管理できなくなった場合に備えて、事前に財産の管理・売却の権限を家族に与える制度です。

財産を「利益を受ける権利」と「管理運用する権利」に分けて、後者を家族に管理・運用してもらう仕組みです。認知症になった場合、管理や処分の方向性について、親自身の意思を最大限反映させることができます。
認知症による財産凍結を避けたいケース
認知症により判断能力が低下すると、本人名義の預貯金の引き出しや不動産の売却などができなくなる「資産凍結」の問題が生じます。家族信託を活用することで、このような事態を防ぐことが可能です。成年後見制度の場合、身内であっても管理人を自由に選べません。また資産を自由に動かしにくいという制約があります。家族信託であれば契約内容に沿って自由に資産を動かせますので、成年後見制度よりも柔軟性が高いといえます。
資産の凍結を防ぎ、柔軟な運用が可能に
家族信託を使うことで資産の凍結を防ぎ、柔軟な運用が可能になるとともに、遺言では一次相続人の指定しかできないが、家族信託では二次相続以降の承継先も指定することができることもメリットです。また、家族信託では信託契約に基づいて財産管理が受託者に一元化され、相続人全員による遺産分割協議が不要になり、相続発生時の手続もスムーズに進めることができます。
相続不動産の流れ
不動産を相続したものの「どうしたらいいかわからない」という方も多いのではないでしょうか。ここでは不動産相続の流れをわかりやすくご紹介します。







遺言書が残されておらず相続人が2人以上いる場合、遺産の分け方を話し合って決める必要があるため遺産分割協議を行います。遺産分割協議にはすべての相続人が参加する必要があります。
遺産分割協議の形式に特に決まりはなく、相続人が直接集まって協議する場合もあれば、メールや電話で話をまとめても構いません。また、遺産分割協議に期限はないため、仮にいつまでも話し合いがまとまらず合意できなくても罰則などはありません。ただし、相続税の申告期限である10ヶ月までに遺産分割協議が終わっていない場合、いったん法定相続分に応じた相続税申告の手続きをとらないと不利益を被ることがある点には注意が必要です。





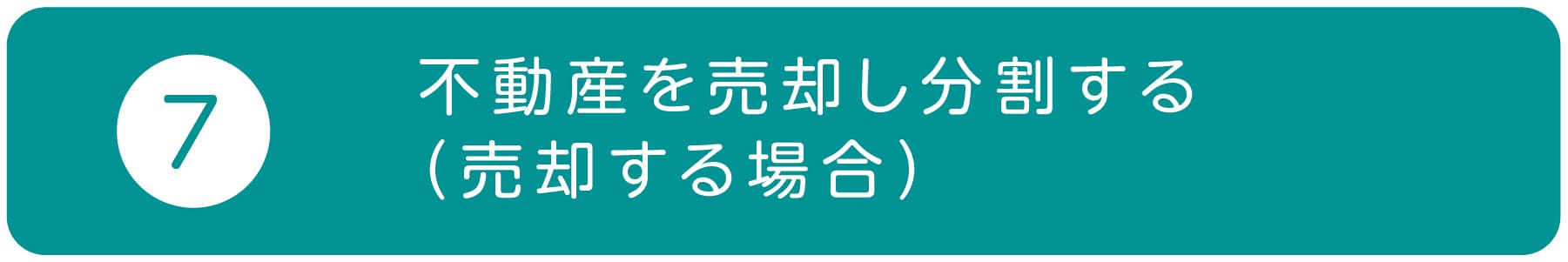


CHECK UP 2
不動産を代償分割する場合、
贈与税はかかる?
遺産分割協議書に「代償分割により代償金を支払う」ときちんと記載しておきましょう。代償財産の種類や金額、支払い期限などを遺産分割協議書に記載することで贈与ではないことが明確になり、贈与税の課税対象にならなくなります。

不動産の相続や売却に必要な書類
不動産の相続に必要となる書類は以下の通りになります。
相続登記の申請書類
相続人全員の住民票抄本
相続人全員の印鑑証明書
被相続人の住民票の除票
不動産の全部事項証明書
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の住民票謄本
被相続人の戸籍謄本(出生から死去まで)
不動産の固定資産評価証明書
空き家を相続する場合の選択肢
空き家を相続した際、活用方法や手放し方を含めて以下の選択肢が考えられます。それぞれのメリットとデメリットを理解したうえで、最適な判断を行うことが大切です。
| 売却する | 空き家を売却することで固定資産税や管理費用などの継続的な負担を解消できます。特に、需要の高いエリアであれば高値で売却できる可能性があります。一方、売却益が発生した場合には譲渡所得税が課されることがあるため事前に税務の確認が必要です。 |
| 賃貸する | 空き家を賃貸物件として家賃収入を得る方法もあります。賃貸物件として貸し出す場合には修繕やリフォームを行い、居住可能な状態にする必要があります。また、入居者管理や賃貸契約に伴う手間も発生するため、不動産管理会社の利用を検討すると良いでしょう。 |
| 居住する | 空き家に自身や家族が居住する選択もあります。思い入れのある実家などの場合は、この選択肢は心理的な満足感を得られるケースも多いです。ただし、老朽化した住宅の場合リフォーム費用が高額になる可能性もあり、費用対効果を見極める必要があります。 |
| 寄与する | 自治体やNPO法人に寄付することで、空き家を有効活用してもらう選択肢もあります。寄付には社会貢献の側面がありますが、寄付先が受け入れる条件を満たす必要があり、手続きも容易ではないことを留意しておきましょう。 |
| 相続放棄 | 空き家を含む財産を相続放棄することで、負担を回避する方法です。相続放棄を選択する場合、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。ただし、他の財産も放棄することになるため、慎重な判断が求められます。 |
不動産相続や売却でかかる費用と税金
相続時にかかる6つの税金
①相続税
相続税は、被相続人が遺した財産を受け継ぐ際に課される税金です。財産には不動産、現金、有価証券などが含まれ、空き家もその一部に該当します。相続税は、基礎控除額を超えた分に対して累進課税が適用されます。
たとえば、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と計算され、これを超える財産部分に税率が適用されます。空き家の規模や立地などによっては不動産の価値が高いとみなされ、相続税負担が高額となることもあるため、事前に不動産評価を確認することが重要です。
②登録免許税
登録免許税は、相続により不動産の所有権を移転登記する際に課される税金です。いわゆる「相続登記」です。原則として固定資産評価額の0.4%が税率として適用されます。
③固定資産税・都市計画税
空き家を所有する限り、毎年固定資産税と都市計画税を支払う必要があります。固定資産税は土地や建物の評価額に基づいて算出され、市町村が課税します。一方、都市計画税は主に市街化区域内の不動産に対して課され、固定資産税の評価額に一定の税率を乗じた額となります。
④譲渡所得税
譲渡所得税の税率は、所有期間によって異なります。所有期間が5年以下の場合には「短期譲渡所得」となり、税率は30%です。5年を超える場合には「長期譲渡所得」となり、税率は15%と低くなります。
例えば、売却価格が1億円、取得費が5,000万円、譲渡費用が100万円の場合、
1億円−5,000万円−100万円=4,900万円
となり、4,900万円に対して
所得税が課税されます。
不動産譲渡所得にかかる所得税と住民税(地方税)は、事業所得や給与所得とは別々に計算されるため、「分離課税」と言われています。不動産を譲渡して利益が出た時は、その利益に対して所得税と住民税が譲渡所得として課税されます。
⑤住民税
(相続した不動産を売却した後に発生する税金)
住民税の税率は、所有期間によって、譲渡所得税の税率と同様に異なります。所有期間が5年以下であれば「短期譲渡所得」となり、税率は9%です。5年超であれば「長期譲渡所得」となり、税率は5%と低くなります。
⑥復興特別所得税
(2037年まで所得税に加算される税金)
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興に必要な財源を確保するための税金です。2037年までの間、所得税額に2.1%が上乗せされます。
相続して売却する場合に
利用できる特例と、
支払う税金を減らすためのコツ
空き家を相続する際、以下の特例や制度を活用することで税負担を軽減できる可能性があります。特に譲渡所得税には税額を減らせる特例が用意されているため、実際に支払う税額は、計算した金額よりも少なくなるケースが多いです。

売却時は譲渡所得
3,000万円特別控除を活用する
この特例では、譲渡所得(売却益)から最大3,000万円を控除できるため、売却後の税負担を大幅に軽減できます。適用条件を満たせば、多くのケースで相続人にとって大きなメリットがあります。ただし、適用を受けるためには一定の条件が必要になりますので、事前に条件を満たすか確認しておきましょう。
適用を受けるための主な条件は次のとおりです。
●相続や遺贈によって
財産を得た者(相続人)であること
●財産を相続するにあたり、
相続税が課されたこと
●相続開始日から
3年10か月以内に売却すること
配偶者控除
被相続人の配偶者は優遇されていて、遺産総額が1億6,000万円までは相続税が控除されます。さらにこれを超えたとしても、法定相続割合相当分まで相続税は控除されるため、ほぼ税金がかかることはありません。
小規模宅地の特例の適用
小規模宅地等の特例は、相続税の負担を大幅に軽減する制度で、被相続人が居住や事業に使用していた宅地を相続する際に適用されます。この特例を利用することで一定の面積までの宅地に対する相続税評価額を最大80%減額可能です。具体的には、居住用宅地であれば最大330㎡まで、事業用宅地であれば最大400㎡までが対象です。結果、相続税が大幅に抑えられ、高額な土地相続の場合には重要な制度となります。
この特例を適用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
| 被相続人がその宅地を居住用 または事業用に使用していたこと | 被相続人が亡くなる直前まで、その宅地を自らの居住用または事業用として使用していたことが求められます。 ただし、被相続人が老人ホームなどに入所していた場合でも、一定の要件を満たせば適用対象となることがありますので、詳しくは専門家に確認することをお勧めします。 |
| 相続人がその宅地を 継続して利用すること | 相続人が相続後も引き続きその宅地を居住用または事業用として使用することが必要です。たとえば、被相続人の自宅を相続した場合、相続人自身がその家に住み続けることが求められます。 事業用の場合も同様に、相続人がその場所で事業を継続することが条件となります。この継続利用の要件を満たさない場合、特例の適用は受けられません。 |
| 相続税の申告期限まで その宅地を保有していること | 相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)まで、相続人がその宅地を所有し続けることが求められます。この期間内に宅地を売却すると、特例の適用が受けられなくなる可能性があります。 したがって、特例の適用を受けるためには、少なくとも申告期限までは宅地の所有と使用を継続することが重要です。 |
| 被相続人と生前に同居していること | 原則として、被相続人と生前に同居していた親族が相続する場合に、小規模宅地の特例を受けることができます。一方で、「家なき子特例」を利用する場合は、必ずしも同居が必要ではありません。 |
家なき子特例について
「家なき子特例」とは、一定の条件を満たすことで同居していなくても特例が受けられる制度です。この特例は、自宅を所有していない相続人に対して適用されます。この特例を利用することで、大きな税負担を避けることが可能です。ただし、特例適用には事前の計画と必要書類の準備が重要です。加えて、この特例の適用状況はケースバイケースで異なるため、士業の方のアドバイスを受けることをお勧めします。
家なき子特例は、以下の要件を満たす場合に適用されます。
●相続人自身や配偶者が相続開始前3年以内に、
自らの所有する住宅に住んでいなかったこと。
(賃貸住宅に住んでいる場合など)
●被相続人の居住用宅地を相続し、
自らの居住用として使用すること。
●過去に同一生計内の親族から
住宅を贈与されたことがないこと。
参照 朝日新聞デジタル:https://www.asahi.com/ads/sozoku_vs/column/tax/25/
参照 国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
【おさらい】不動産は相続後
3年以内の売却がおすすめ
相続税を費用にする特例は、譲渡所得の計算時に3,000万円を控除でき、課税対象額を抑えられる制度です。不動産を相続後3年以内に売却すると「相続税の取得費加算の特例」が適用され、相続不動産の売却により生じた譲渡所得から、相続税の一部を「売却にかかった費用」として差し引けます。
特例が適用されると、課税対象となる金額がさらに少なくなることに。結果的に、譲渡所得税の節税につながります。
譲渡所得 = 売却金額 −(取得費 + 譲渡費用)− 3,000万円(特別控除)
⇒ 譲渡所得が3,000万円以下なら譲渡所得税は課税されない
つまり、特例を活用し被相続人の空き家を売却すれば、譲渡所得が3,000万円以下なら譲渡所得税は課税されないということです。3年以内に土地を売却するためにはスムーズな遺産分割と早めの行動が必要です。相続した不動産を売却して、譲渡益が発生した場合には、確定申告を行う必要があります。不動産を売却する際には、取得費の確認や特別控除の適用要件の確認など、確認すべき事項が多く、確定申告書に添付する書類も多いため、手続きが煩雑になりがちです。
そのため、不動産を売却した場合には、確定申告が必要かどうか、また、特別減税の適用を受けられるかどうかなど、必要な手続きを正しく行うためにも、早めに士業の方に相談することをおすすめします。
※他の相続人が相続税を払っており、土地を引き継いだ人に相続税が発生していなければ特例は利用できません
※空き家の3,000万円の特別控除との併用はできません。